会長挨拶
令和四年の一斉改選を経て、会長に就任しました高山 学でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 民生委員・児童委員活動のスローガン「支えあう 住みよい社会 地域から」は、全国約23万人の民生委員・児童委員の合言葉で、岡山市では、1,242人の仲間が活躍しています。また、岡山市内には69の地区民生委員児童委員協議会があり、我がまちの福祉課題に取り組んでいます。
少子高齢化と人口減少により地域が高齢化すると地域力も脆弱となり、福祉課題が複雑多岐化します。加えて、コロナ禍で自治体主催の行事が規模縮小・中止となった影響が学校・園や地域にも及び、地域コミュニティが希薄になっています。この改善も必要です。
昨今、コロナ禍前の日常を取り戻しつつあります。民生委員・児童委員活動におきましては、身につけた感染対策をしつつ、顔の見える活動に取り組み、福祉課題の解決に向け、地域の町内会や諸団体と協働して実情を把握し、関係機関・団体に繋ぎ、健康で文化的な生活と安全安心なまちづくりに努めます。 私たちは、児童虐待の防止をはじめ福祉の充実と発展に寄与して参ります。 皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
岡山市民生委員児童委員協議会 会長
高山 学

制度と概要
民生委員・児童委員とは、地域住民の立場にたって地域の福祉を担うボランティアです。
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された特別職非常勤の地方公務員です。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。給与の支給はなく、ボランティアとして活動しており、任期は3年です(再任が可)。 全国共通の制度であり、約23万人の民生委員・児童委員が活動しています。
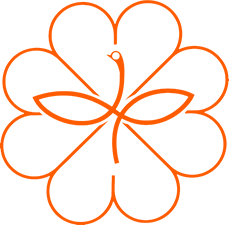
民生委員制度の歴史
民生委員制度発祥の地 おかやま
民生委員制度は平成29年に100周年を迎えた歴史と実績を有する制度です。
民生委員制度は、大正6年に岡山県で創設された「済世顧問制度」、翌年に大阪府で始まった「方面委員制度」が起源とされます。以来100年にわたり、住民の一員として、住民視点に立って安心して住み続けることができる地域づくりに取り組んでいます。
全国に先駆けて岡山県で設置された済世顧問制度
大正3年から大正8年まで岡山県知事を務めた当時の笠井信一によって、済世顧問制度は創設されました。大正5年5月18日に開かれた地方長官会議の際、県下の教育や貧困者の状況について天皇から尋ねられました。当時は、第一次世界大戦時の好景気であり、貧困者の状況をまとめた資料はなかったため、地方長官会議から戻った笠井は、県下の貧困者の実態調査を行うとともに、諸外国の防貧対策も含め制度や理念を研究しました。その際には藤井靜一からも話を聞いたと言われています。 そして、「済世顧問制度」としてまとめ、議会での審議や県下の郡市長並びに警察署長会議での説明等を経て、大正6年5月12日に「済世顧問設置規程」(岡山県訓令第10号)が公布されました。「民生委員の日」は、この規程公布日に由来しています。

基本姿勢・基本的性格・原則
民生委員・児童委員は
地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。
自らも地域住民の一員として、担当の区域において高齢者や障がいのある方の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけなどを行っています。福祉に関するさまざまな相談に応じます。相談内容に応じて、必要な支援が受けられるよう、地域の専門機関とのつなぎ役になります。民生委員・児童委員には法に基づく守秘義務があります。
主任児童委員は
子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。
主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、全国で約2万1千人が活動しています。担当区域をもたず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
